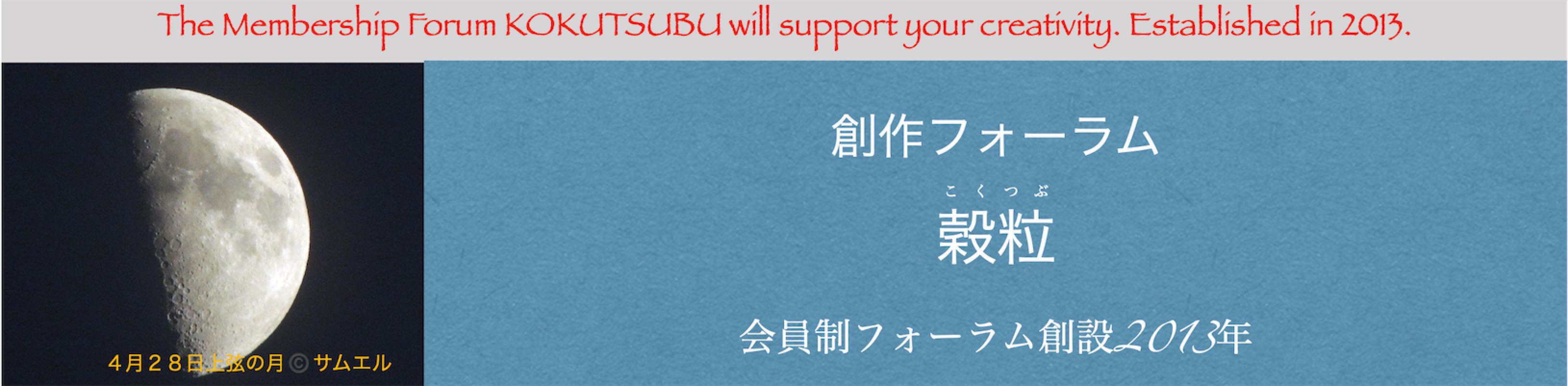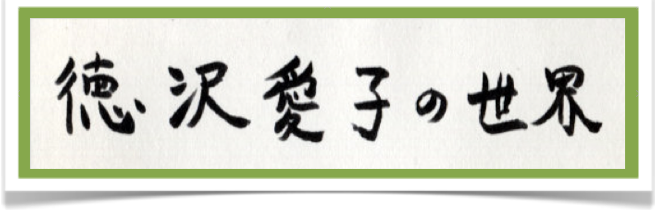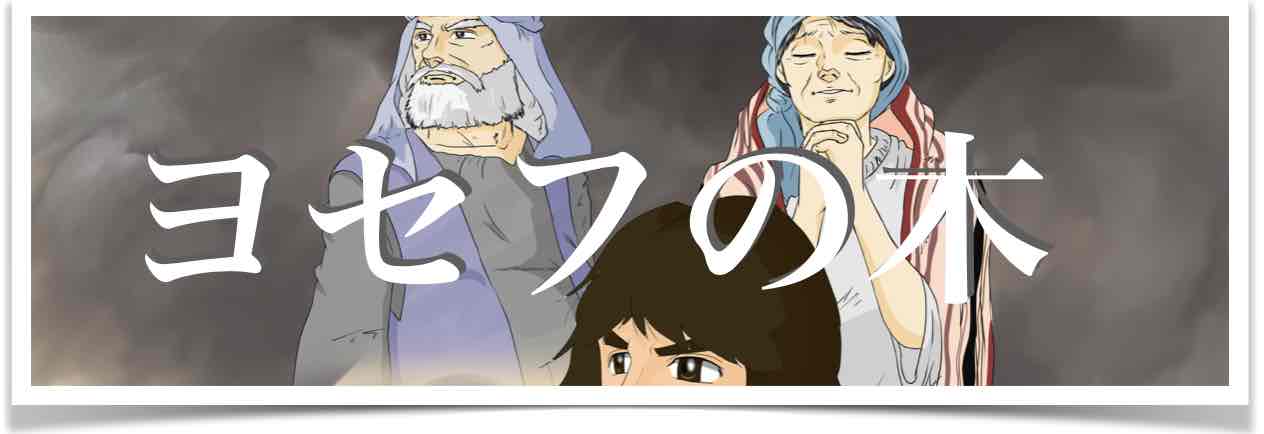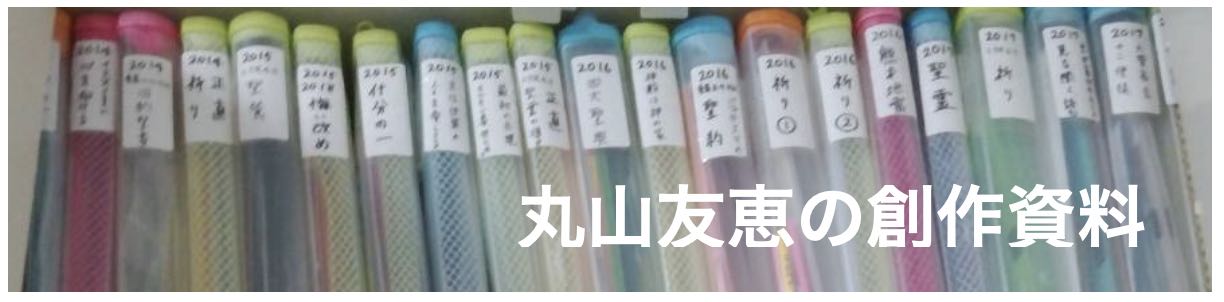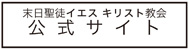15102301 徳沢 愛子
2015.10.23 エッセイ「死はお金を持って何気なく」投稿者:徳沢 愛子
叔母は死んでいた。しょたれた肌布団をかき抱くようにして。テレビは乾いた音を流していた。飾り気のない電気スタンドは、40ワットの光を灯(とも)らせていた。一パイ飲み屋をやってきて50年、捨てることのなかった貧しい50年は、4畳半を物の山にしていた。谷間に敷かれた1枚の布団は、ただ一つの寂しい聖地であった。金沢のK町の歓楽街、奥まった敷地の一隅、開店休業の店の中は乱雑におかれた食器類、一人用の手鍋、調味類、古新聞、ビニール袋、風呂用品、空の酒ビン、みの出た椅子、スズ虫のケース、火事場のような有様であった。死の三日前、訪ねた昼下り、戸に手をかけると、ガラガラと拍子抜けのように軽く開いた。声をかけた。返事がない。あるのは闇だけ。と、人の気配。ゆっくりこちらに向く。ゾクッとする。おしっこの臭い。無表情のやせた叔母が坐っていた。体をこちらに向ける。〈いたんかァーびっくりしたァ、返事してェ〉ママゴトのようなチャブ台の上に、スーパーで売っている一人前用の大根と油揚げの煮物と赤飯。どちらも殆ど手をつけていない。1年前、歯肉ガンの大手術。歯茎の代わりにハメ物充填、食べ物はすべてみじん切り。片頬は胸の白い皮フをつぎはぎし、手塚治虫のブラックジャック風、退院後、直ちに老人ホーム入所。〈食べること、寝ること、悪口をいうことが仕事の老人たちとは、つきあいきれない〉と読書三昧。週に3、4日は、この荒れ放題のわが飲み屋へご帰還の生活リズム。1階も2階も、物の洪水、その中でブクブクと好きなテレビ水戸黄門などなど。〈おばちゃん大丈夫?こんな固い赤飯たべられるが?ね、ホームへ帰ろう。今すぐ車で送るから〉〈あの人、いびきヤカマシイッとすごい顔して怒るうッ〉目が据わっている。〈手術の後遺症で出るいびきやからどうしようもないのにね。ホームへいって、今度こそ部屋を変えてもらうように言ってあげるから、安心して帰ろうね〉叔母はゆっくり台の上の白い紙きれを見せる。日付がズラリ、その横に30万、20万、50万、30万、100万。満期がくる定期預金の金額らしい。いよいよ頭にきたのか、ひとり身の人にそんなにお金あるはずない。〈あさって満期になるこの50万円の分、もらってからホームに帰る〉それでもいつもと違う雰囲気なので帰ることをすすめるも、〈いや、このお金をもらってから、きっと帰る〉、やがて現状保留のまま、〈じや帰るけど、満期の16日にはきっとホームに帰ってきてね〉、彼女はゆっくり立ち上がってきて戸口に立つ。上は綿入れの半てん、下はラクダ色の5分ズロース。股がおしっこで濡れている。一瞬私は迷う。あれだけお金の管理もきちんとやっているのだから、全くの認知症でもあるまい。明日にでも来てみよう。手を振って車を出す。叔母少し笑ったような表情で手を振る。これが最後の姿であった。
私は目の不自由な義父との、一時同居中で、外出しにくく3日後に出掛ける。そしてこの発見である。菓子パン3個、叔母の昼食にと買う。お昼時、明るい陽春のよい日和り、鍵がかかっている。いつもスペアキーを預かってもらっている2軒隣のタバコ屋さんに行って、鍵をもらってくる。戸を開ける。薄闇に慣れるまでしばし。階下には人の気配なし。〈おばちやーん、おばちやーん〉同じトーンで呼びかけながら、細い暗い急な階段を登って2階へ。階段のてっぺんから障子のない部屋をのぞく。テレビは別世界の人のようにしやべり、スタンドはぽおっと光っている。叔母が横になっている。ド近眼の私、表情がよくわからない。実に静かだ。異様な静けさだ。突然、怖さが全身頂上にのぼりつめる。階段をかけ下りる。店を飛び出す。〈タバコ屋さーん〉タバコ屋さんかけ上がる。〈花村さん、花村さん。あれェェ、冷めとうなっとる〉タバコ屋さんはスカートの裾ひるがえし、ドタドタかけ下りて警察へ連絡。私は近くの小児科医院へ走る。医者と看護婦走る。医者かがみこんで叔母を見ただけ。さわらない。看護婦さん立っているだけ。〈おそらく心臓疾患でしょう〉。私もさわらない。さわれない。これが何かと40年余、身内のつきあいをしてきた姪の私か。驚く。肉体を抜けた魂、天井あたりに漂い見下ろして、立腹しているだろうなと考えながら、叔母を見つめている。医者と看護婦、あとで死亡診断書書いておくといって帰る。私一人残される。しゃがむ場所もない。死んでしまっている叔母の頭の所に電話機、顔を見ないようにして実家の父に電話。父82歳〈アッリャリャ(沈黙)そうかい、わかった、畑行っとるばあさんに知らせてくる。お前そこにおってくれ〉。屈強な警官4人来る。新聞記者をまいてきたという。そうだ、犯罪のにおいがする72歳の老婆の孤独死はニュースになるなぁとどこかで考えている。警察は今から裸にして写真をとるから、あんたは外へ出とってくれという。そんなことをしなければならないのか。叔母がかわいそう、とどこかで文句をいっている。ふわふわと外へ出る。2階の薄暗いすりガラスを外から見上げる。桜は満開の時期。風の吹くたびちらちら舞い散っていることだろう。腕時計は1時を指している。空腹感はない。いつの間にか葬儀屋が私の横に立っている。神業のような早さだと感心する。兄がかけつける。鼻の頭に汗をかいている。今日はそんなに暑かったか。そういえば今日は横浜にいる二男の誕生日だった。警官が呼ぶ。上がる。狭いので重なるように体格のいい人たちが立っている。外傷なし。犯罪とは無関係。何か黒っぽい着物を着せてくれという。古い取っ手をカタカタいわせてタンスをあける。昔の匂いがプンと立ち昇る。底の方に黒い喪服がある。兄に渡す。かけてあった布団をまくると裸にされた叔母はしなびた少女のように、小さく真直ぐ横たわっていた。懐かしい丸味をみせていた乳房は、わずかなふくらみで両脇にずれていた。黒ずんだ両手が胸で組まれていたが、柔らかいのですぐほどけそうな気配であった。商売上お酒を毎日飲んでいたから、ふにやふにやなるのだろうか。兄と葬儀屋がそれを着せる。見ていると両腕は長いコンニャクのように柔らかい。何やかやと世話して来た私が、この期に及んで着物も着せようとしない。わからない。本質は冷酷な人間であったのか。情けないと思い続けるも手が出ない。そこらあたりの物を両脇に押しやって納棺。はいていたズボンのポケットには千円札6枚が入っていた。警官がビニール袋に入れ、私に渡し、書類に署名させる。寝棺を担いでいくのは兄、組合のひげのある理事長さん。感情のない無機質の葬儀屋2人、金ピカの掛け布を寝棺に掛けて、一躍、叔母はそれらしく整って出ていく。なかなかの美人だったもの、きちんとしなくちゃ。
小さな鍋に赤飯のおかゆ、そのまま手つかずにある。3日前、赤飯を前にして殆ど食べず、おかゆにしてもそれも一口も食べず、衰弱死したのではなかろうか。あの時、無理にでも老人ホームへ連れ帰っていれば、こんなことにならなかったのかと、悔いも湧いてくる。いや然し、叔母らしい死に様でなかったかとも思い直す。きっとこれでよかったのだ。
さて葬式代を探さねばならぬ。翌日、タンスやこことおぼしき所を家探しする。こことおぼしき所には、通帳などなし。大事な印鑑は死人の指からとった金の指輪。
遂に葬式代が出てきた。意表をつく隠し場所だった。夜ともなれば、コワモテのおニイさんたちが、店の前で客引きしている有様であったから、さもあらんという所かもしれない。古新聞やら、何やらごちやごちやに重ねてある隅っこに、ショッピングカーがあった。その中には白いビニール袋がわんさとつめこんであった。その底に通帳など貴重品全財産が入った袋があったのである。アッパレおばちやんである。確かにあの紙きれのメモは真実であった。中年になった頃から、叔母はいつも手製のピラピラのズボンをはいていた。近所の仲良しの人の話では、ズボンは貞操を守るためであったらしい。そのズボンのポケット、また手製のエプロンのポケットは、特別製で深い深いポケット。その中にはいつも万札など入っていた。そうして貧しい生い立ちの叔母は、一つの幸福を味わっていたのだ。女一人、思いがけないほどの財産をためていた。当時、70歳になったばかりの叔母は、歯肉ガンの手術費は殆どタダであったし、それまで健康そのものであったから、時たまの小旅行以外は余りお金を使うことはなかったようだ。いつも事務服にズボン姿のスタイルであった。あんな姿で通したのは年老いてからなのだろう。若い頃は美しい愛らしい顔と豊かな胸で、客足をつかんでいたのかもしれない。独立自尊の精神で念願のお金持ちになり、そして叔母は貧しく逝った。老人ホームへ帰って、4畳半に2人、畳をたたいてヤカマシイ!と怒鳴る人と居るよりは、集会室のテレビひとつ、自分のラジオひとつ、自由自在に鳴らせぬ、見たりできぬ生活よりは、思うようにみじん切りの料理を食べられなくても、誰にも拘束されない生活で、出来合いのものを買って四苦八苦して食べている方が、彼女にとってどれだけ幸福であったことか。
ささやかな葬式の読経の時、私は心の中で、<おばちやーん>と呼んで、初めて涙を流した。一時期、妻子のある年配の人の愛人となって、寂しさをまぎらわしていた叔母、酔っ払ってその男性はあの階段から落ちて死んだのだ。孤独に負けず、一生懸命お金をためて生きてきた叔母。この現実は春の華やかさとは裏腹であった。あの日肉体を離れたばかりのおばの霊に天井から私の素っ気ない態度を見られたうしろめたさが、今もって暗く尾を引いて私を占領している。悲しむに時があるらしい。すべての事には「時」がある。
ひたすらお金だけ貯えて、その数字を楽しみながら逝った叔母。年に1、2回の友人との温泉旅行。私の子供たちが幼かった頃、カッパえびせんやペロペロキャンデーでほっぺにキスをしてもらった事、そのどれもが叔母を本当の幸福にしなかったのではないか。女の子3人使って華やかに夜を稼いだ叔母、彼女にとってどんな人生であったのだろうか。何が彼女を幸福にしたのだろうか。
あの日と同じ桜が咲き始め、はや1年が過ぎ去ろうとしている。
- 文体が力強いため、そうとう惨めかもしれない状態であるのに、それを感じさせない迫力があって徳沢愛子姉妹の繰り出す言葉の持つ不思議な力にパンチを喰らってしまいます。一人で老いて一人で死んで逝く、立派な叔母さまでしたね。「やっぱり、愛子ちゃんが来てくれたァ」と喜ばれたことでしょう。このご時世白骨化したっておかしくないのです。
「谷間に敷かれた一枚の布団はただ一つの聖地であった」かくも悲しくかくも美しい表現があるでしょうか。 -- 岸野みさを 2015-10-24 (土) 19:48:42